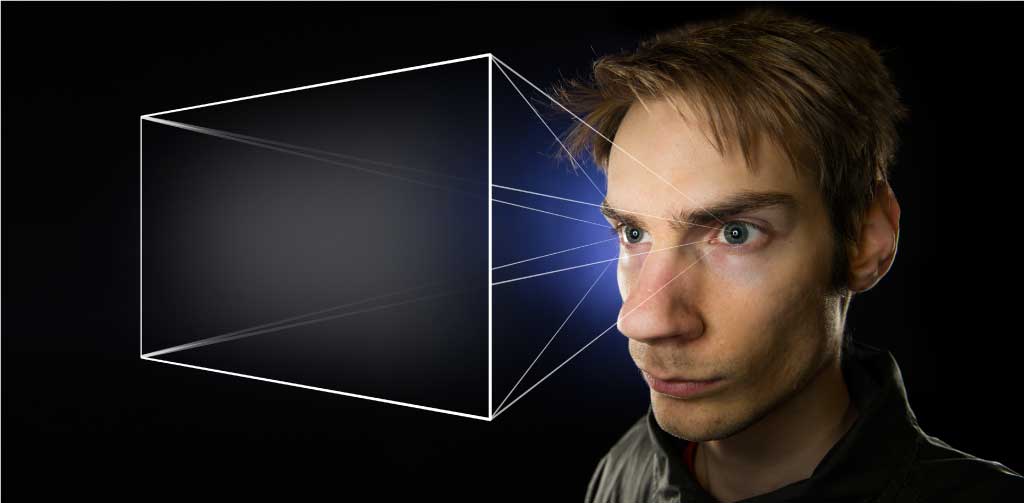シュレディンガー方程式は、量子力学を学ぶうえで初めに出てくる重要な方程式です。この方程式の解は波動関数と呼ばれていて、例えば水素原子における電子のふるまいは波動関数として厳密に記述することができます。
それ以外の、他電子原子や2原子以上からなる分子は残念ながら水素原子のように電子の動きを厳密に解くことはできませんが、近似的には解けます。この近似的な解も、シュレディンガー方程式が関わってきます。
ということで、今回は1次元の場合で古典的波動方程式の解からシュレディンガー方程式を導くところまでを解説していきたいと思います。
古典的な一次元の波動方程式とその解
結論から言うと、以下の式がシュレディンガー方程式です。
シュレディンガー方程式は、古典的波動方程式とド・ブロイの提唱した物質波の考えの2つをもとに得ることができます。
まず、両端が固定された弦が振動しているとき、時刻\(t\)の位置\(x\)における変位\(u(x,t)\)は以下の波動方程式を満たします。
そしてこの方程式を変位\(u(x,t)\)について解けば、以下の解が得られます。
このとき、\(n\)は自然数、\(A_n\)はnに依存する係数、\(v\)は弦を伝わる波の速度、\(l\)は弦の長さ、\(\phi_n\)はnに依存する位相角です。古典的な波動式の解き方は以下の記事で解説しているので、そちらを参考にしてください。
この波動方程式の解(3)は、\(\sum\)の中身が位置\(x\)に関する正弦波と時間\(t\)に関する正弦波の積で表されています。位置と時間の関数がそれぞれ独立しているのです。したがって、\(u(x,t)\)を以下のように書くこともできます。
このとき、\(\omega\)は角振動数です。時間部分の関数が\(\sin\)から\(\cos\)に変わっていますが、これら2つは位相が異なるだけで互いに置き換え可能です。この(4)式を波動方程式の(2)式に代入してみます。
移項と因数分解をして、
\(\cos{\omega t}=0\)だと変位\(u\)が無意味な解になってしまうため、
になります。ここで、角振動数\(\omega=2\pi\nu\)および波の速度\(v=\nu\lambda\)であることから、代入すると、
を得ます。
ド・ブロイ波長
(6)式をからシュレディンガー方程式(1)を得るために、ド・ブロイの物質波の考えを利用します。
粒子の全エネルギーは、運動エネルギー\(\frac{1}{2}mv^2\)と位置エネルギー(ポテンシャルエネルギー)\(V(x)\)の和に等しいので、
粒子の運動量\(p=mv\)であるため、代入して\(v\)を消去すると、
さらに、式変形して\(p\)について解くと、
になります。
ところで、当時はヤングの実験や光電効果の実験によって、光の波動と粒子の二重性が見出されていました。アインシュタインの相対性理論によって、光子の波長\(\lambda=h/p\)であることも示されていました。
ド・ブロイは、この式が光だけでなく物質に対しても成り立つと主張しました。このとき成り立つ物質の波長\(\lambda=h/p=h/(mv)\)は、ド・ブロイ波長と呼ばれます。
(9)式をド・ブロイ波長に代入すれば、
となります。
シュレディンガー方程式
それでは、(10)式を(6)式に代入してみます。
ここで、\(\hbar=h/2\pi\)を定義すれば、
となります。これがシュレディンガー方程式です。
この方程式(12)には、時間に依存する項が見られません。それは、(5)式を得る際に\(\cos{\omega t}\)が消えたからです。
そのため、(12)式のシュレディンガー方程式は特に、時間に依存しないシュレディンガー方程式と呼ばれています。
一方で、時間に依存するシュレディンガー方程式はまた別の仮説から導き出すことができます。
最後に、(12)式の両辺を\(2m / \hbar^2\)で割って\([ \, ]\)を展開し、\(E\psi(x)\)を右辺に移項すると、
(13)式は、シュレディンガー方程式を固有値問題として捉える際に見られる形になります。
参考文献
D.A.McQuarrie J.D.Simon(1999), 『物理学(上)-分子論的アプローチ-』, 東京化学同人, pp.79-81