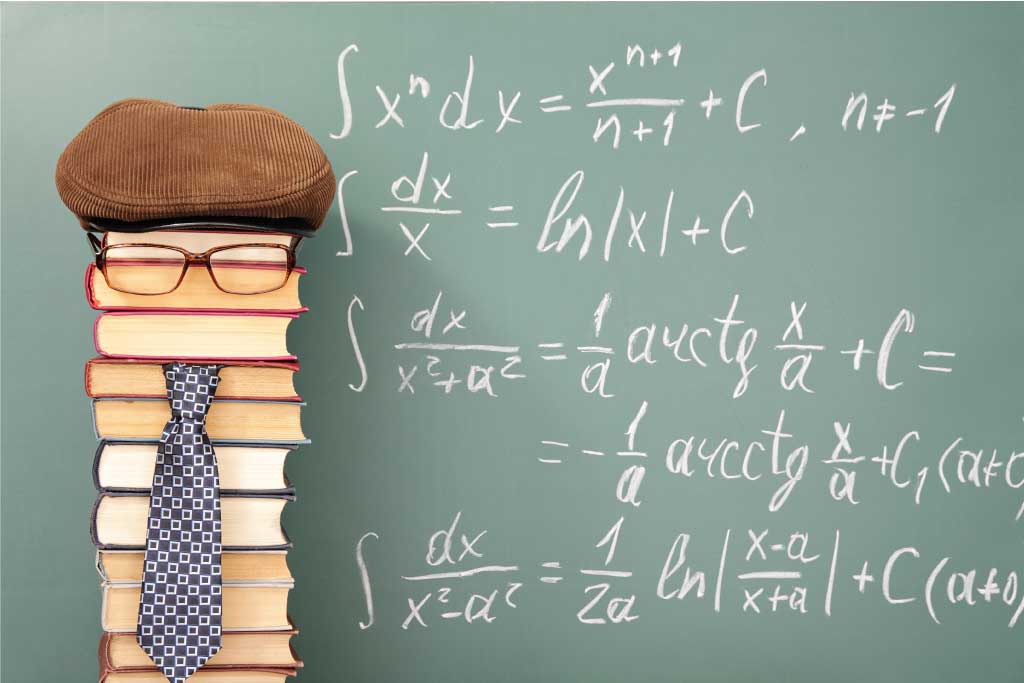今回はリーマン積分を定義し、リーマン積分が可能であるための必要十分条件に関する定理を紹介します。
この記事では、以下のように有界な関数\(f\)を仮定します。
閉区間\([a,b]=\{x \vert s \le x \le b\}\)上で有界な関数\(f \: : \: [a,b] \to \mathbb{R}\)は、
を満たしているとします。というのも、このように有界な関数に限って考えないと、リーマン積分を定義するにあたってダルブー和が定義できなくなってしまうからです。
この仮定が成り立たない関数については、別の記事で解説します。
それでは、有界な関数\(f\)のリーマン積分を定義しましょう。そのために、まずはダルブー和の定義と関連する2つの補題を証明します。
ダルブー和の定義
まずは閉区間\([a,b]\)を小さい部分区間に分割します。
つまり、\(a = x_0 \lt x_1 \lt x_2 \lt \cdots \lt x_n =b\)を満たすように分割の集合、
をおきます。そして、部分区間の長さを\(\delta_i = x_i – x_{i-1}\)で定義します(\(1 \le i \le n\))。
さらに、
をそれぞれ、下ダルブー和と上ダルブー和と定義します。このとき、\(f_i\)と\(F_i\)はそれぞれ、
です。これらの定義から、明らかに\(s(D) \le S(D)\)となっていて、関数\(f\)の積分をこれら2つのダルブー和で挟むのが定義の方針です。
また、\([a,b]\)の分割\(D^\prime\)が\(D\)の点をすべて含むとき、\(D^\prime\)を\(D\)の細分といいます。
である。
分割\(D\)に点を1つ加えると、下ダルブー和の値は大きくなるか変化しません。さらに、上ダルブー和の値は小さくなるか変化しません。したがって、上の補題1が得られます。
が成り立つ。
分割\(D^\prime = D_1 \cup D_2\)をとれば、先ほどの補題1より、
が得られます。上の2つの不等式を組み合わせれば補題2の不等式が得られます。
これら2つの補題から分かることがあります。
まず、補題2の不等式が、分割\(D_2\)の固定された任意の分割\(D_1\)に関する式であると捉えましょう。すると、\(s(D_1)\)は\(S(D_2)\)によって上から押さえられていることから、\(s(D_1)\)は上に有界であり、ゆえに上限が存在します。
逆に、補題2の不等式が、分割\(D_1\)の固定された任意の分割\(D_2\)に関する不等式であると捉えましょう。すると、\(S(D_2)\)は\(s(D_1)\)によって下から押さえられていることから、\(S(D_2)\)は下に有界であり、ゆえに下限が存在します。
そこで、\(s(D)\)の上限を下積分、\(S(D)\)の下限を上積分と呼ぶことにします。加えて、下積分と上積分の記号を以下のように取り入れます。
これでいよいよリーマン積分を定義することが出来ます。
リーマン積分の定義と、積分可能であるための必要十分条件
で表すことにする。
そして、有界関数\(f\)がリーマン積分可能であるための必要十分条件を与えます。
である。
証明
上積分と下積分が一致するならば、下ダルブー和の集合と上ダルブー和の集合が任意の近さにあります。逆に、下ダルブー和の集合と上ダルブー和の集合が任意に近さにあるとすれば、上積分と下積分は一致します。よって、2つの仮定は同値の関係にあります。
また、下ダルブー和の集合と上ダルブー和の集合が任意の近さにあることは、すなわちすべての\(\varepsilon \gt 0\)に対して分割\(D_1\)と\(D_2\)が存在して、\(S(D_2) \: – \: s(D_1) \lt \varepsilon\)を満たします。
このとき、\(\tilde{D} = D_1 \cup D_2\)と置けば、補題1より\(S(\tilde{D}) \: – \: s(\tilde{D}) \lt \varepsilon\)を満たすことが分かります。
有界関数\(f\)がリーマン積分可能であるための必要十分条件として、以下のような定理も与えられています。
である。このとき、\(\mathscr{D}_\delta\)は\(\max_{\;i} \delta_i \le \delta\)を満たすすべての分割の集合である。
証明
まずは十分性を証明します。
の仮定から、直ちに、
も満たすことが分かります。したがって、先に証明した定理1より十分性は成り立ちます。
次に、必要性を証明します。
\(\varepsilon \gt 0\)の値を固定すれば、関数\(f\)が積分可能であるという仮定より\(\tilde{\Delta} = S(\tilde{D}) \: – \: s(\tilde{D}) \lt \varepsilon\)を満たす分割\(\tilde{D}=\{\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \cdots , \tilde{x}_\tilde{n} \}\)をとることが出来ます。
また、任意の分割\(D \in \mathscr{D}_\delta\)に対して、\(\Delta = S(D) \: – \: s(D)\)を置きます。
そこで、分割\(D\)に分割\(\tilde{D}\)の元を1つずつ加えて、和集合\(D^\prime = D \cup \tilde{D}\)を作ることを考えましょう。このとき、\(\Delta^\prime = S(D^\prime) \: – \: s(D^\prime)\)とします。
分割\(D\)に\(\tilde{x}_\tilde{i}\)を加えれば、\(x_i \le \tilde{x}_\tilde{i} \le x_{i+1}\)の評価が得られます。\(x_{i+1} \: – \: x_i \le \delta\)と\(\mid f(x) \mid \le M ((1)式より)\)から、\(\Delta\)は最大で\(\delta \cdot 2M\)だけ減少します。これを繰り返して分割\(\Delta^\prime \)を作ることを考えれば、
となります。
また、分割\(\Delta^\prime\)は分割\(\tilde{\Delta}\)の細分ですから、補題1より\(\Delta^\prime \le \tilde{\Delta} \lt \varepsilon\)を満たします。
そこで、\(\delta \le \varepsilon / 2(\tilde{n} \: – \: 1)M\)とおけば(4)式の評価が進んで、
を得ます。\(\Delta\)の値を任意に小さくすることが分かったので、必要性も成り立ちます。
リーマン和
分割\(D = \{x_0 , x_1 , x_2 , \cdots , x_n\}\)に対して、\(x_0 \le \xi_1 \le x_1 \le \xi_2 \le x_2 \le \xi_3 \le \cdots\)を満たす\(\xi_1 , \xi_2 , \cdots , \xi_n\)をとります。
このとき、
をリーマン和といいます。(2)式で定義した\(f_i\)及び\(F_i\)と組み合わせれば、\(f_i \le f(\xi_i) \le F_i\)の評価を得ます。したがって、\(s(D) \le \sigma \le S(D)\)も成り立ちます。
このことから、\(\max_{\;i} \delta_i \to 0\)のときの\(\sigma\)の極限はリーマン積分になります。すなわち、
です。