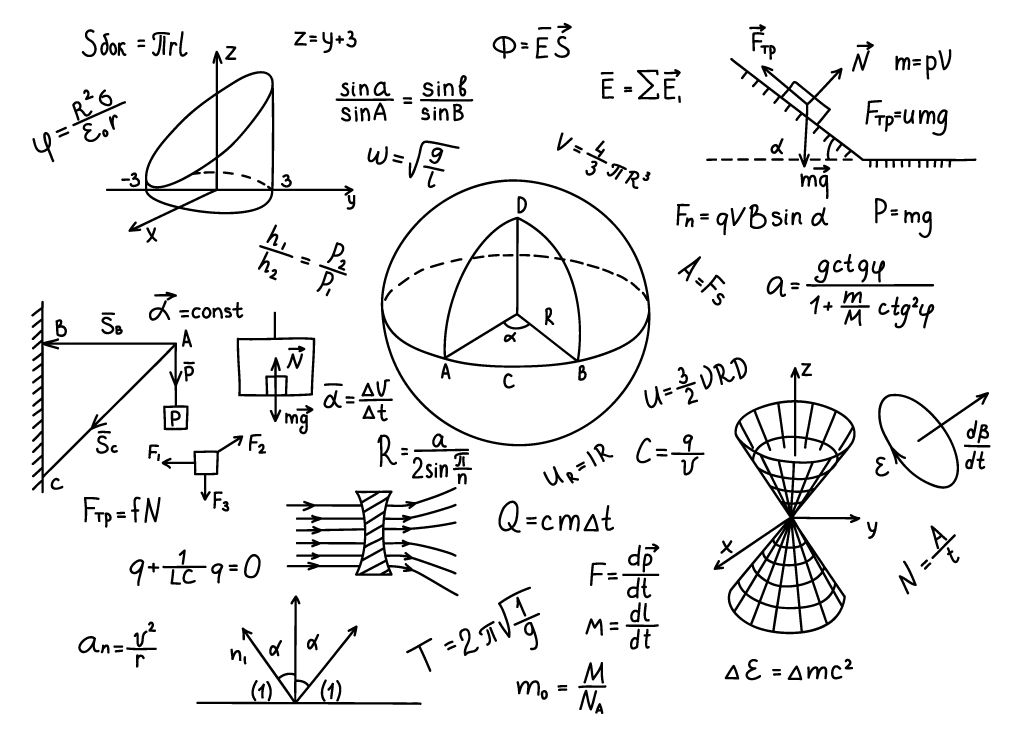水素原子に関するシュレディンガー方程式は厳密に解くことができます。今回は、水素原子のシュレディンガー方程式を立てることから始めて、動径方程式および波動関数の角度依存式が剛体回転子のシュレディンガー方程式と一致することを確認します。
シュレディンガー方程式
まず、時間に依存しない3次元のシュレディンガー方程式を以下に示します。
$$\hat{\,H}\psi (x,y,z)=E\psi (x,y,z) \tag{1}$$
このとき、\(\psi(x,y,z)\)は運動する粒子の波動関数、\(E\)は粒子の全エネルギー、\(\hat{\,H}\)はハミルトン演算子(ハミルトニアン)で、
$$\hat{\,H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(x,y,z) \tag{2}$$
で与えられます。このとき、\(\hbar^2=h/2\pi\)で\(h\)はプランク定数、\(m\)は粒子の質量、\(V(x,y,z)\)は粒子のポテンシャルエネルギー、\(\nabla^2\)はラプラス演算子(ラプラシアン)と呼ばれるもので、
$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{3}$$
で与えられます。シュレディーンがー方程式の導出については以下の記事にて解説していますので参考にしてください。
参考:時間に依存しないシュレディンガー方程式を導出しよう
水素原子のシュレディンガー方程式
それでは、水素原子のシュレディンガー方程式を解いていきます。
水素原子は、核を原点としてそのまわりを1個の電子が回転運動しているモデルと見なすことができます。核には陽子が1個含まれているので、核と電子のあいだにクーロン力が働きます。すると、このモデルにおける電子のポテンシャルエネルギーは電位に等しいので、
$$V(r)=-\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r} \tag{4}$$
このとき、\(\varepsilon_0\)は真空における誘電率、\(r\)は核と電子のあいだの距離、\(e\)は電気素量です。電気素量は1個の陽子または電子の電気量と等しいです。電子の質量を\(m_{\,e}\)とおいて(4)式を(2)式に代入すれば、
$$\hat{\,H}=-\frac{\hbar^2}{2m_{\,e}}\nabla^2-\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r} \tag{5}$$
前項では3次元直交座標系のシュレディンガー方程式を示しましたが、水素原子モデルでは電子が回転していることから、極座標系で解きます。
 Wikipediaより
Wikipediaより
$$(x,y,z)=(r\sin \theta \cos \phi , r\sin \theta \sin \phi , r\cos \theta) \tag{6}$$
とおくことによってラプラス演算子は、
$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta\frac{\partial}{\partial \theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}(\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}) \tag{7}$$
になります。この極座標変換によって変数は\(x,y,z\)から\(r,\theta,\phi\)になり、(5)式を(1)式に代入すれば、
$$[-\frac{\hbar^2}{2m_{\,e}}\nabla^2-\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}]\psi (r,\theta ,\phi )=E\psi (r,\theta ,\phi ) \tag{8}$$
[ ]内を展開して、
$$-\frac{\hbar^2}{2m_{\,e}}\nabla^2\psi (r,\theta ,\phi )-\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}\psi (r,\theta ,\phi )=E\psi (r,\theta ,\phi ) \tag{9}$$
これに極座標変換したラプラス演算子(7)式を代入すれば、
$$\begin{align} -\frac{\hbar^2}{2m_{\,e}}[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta\frac{\partial}{\partial \theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}(\frac{\partial^2}{\partial\phi^2})]\psi (r,\theta ,\phi &) \\ -\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}\psi (r,\theta ,\phi )=E\psi (r,\theta ,\phi &) \end{align} \tag{10}$$
左辺第1項の\(\psi (r,\theta ,\phi )\)を[ ]内に入れて、
$$\begin{align} -\frac{\hbar^2}{2m_{\,e}}[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\psi }{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta\frac{\partial\psi }{\partial \theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}(\frac{\partial^2\psi }{\partial\phi^2})&] \\ -\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}\psi (r,\theta ,\phi )=E\psi (r,\theta ,\phi &) \end {align} \tag{11}$$
さらに、両辺に\(2m_{\,e}r^2\)をかけて右辺の項を左辺に移項すれば、
$$\begin{align} -\hbar^2\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\psi }{\partial r})-\hbar^2[\frac{1}{\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta\frac{\partial\psi }{\partial \theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}(\frac{\partial^2\psi }{\partial\phi^2})&] \\ -2m_{\,e}r^2[\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}+E]\psi (r,\theta ,\phi )=&0 \end {align} \tag{12}$$
となって、左辺の第1項および第3項が\(r\)に関わる式で第2項が\(\theta\)と\(\phi\)に関する式といった形に別れました。このような方程式(12)の形から、変数分離法が利用できると予想できます。すなわち、波動関数\(\psi (r,\theta ,\phi )\)が、
$$\psi (r,\theta ,\phi )=R(r)Y(\theta ,\phi ) \tag{13}$$
の関数になると仮定します。これを(12)式に代入します。このとき、
$$\begin{align} \frac{\partial \psi }{\partial r}&=Y\frac{dR}{dr} \\ \frac{\partial \psi }{\partial \theta }&=R\frac{\partial Y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial^2 \psi }{\partial \phi^2 }&=R\frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \end{align} \tag{14}$$
になることに注意すれば、(12)式は、
$$\begin{align} -\hbar^2\frac{\partial}{\partial r}(r^2Y\frac{dR}{dr})-\hbar^2[\frac{1}{\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta \cdot R\frac{\partial Y}{\partial \theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}(R\frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2})&] \\ -2m_{\,e}r^2[\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}+E]R(r)Y(\theta ,\phi )=&0 \end {align} \tag{15}$$
両辺を\(R(r)Y(\theta ,\phi )\)で割って第1項および第3項を1つにまとめれば、
$$\begin{align} -\frac{\hbar^2}{R(r)}&[\frac{d}{d r}(r^2\frac{dR}{dr})+\frac{2m_{\,e}r^2}{\hbar^2}(\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}+E)R(r)] \\ -&\frac{\hbar^2}{Y(\theta ,\phi )}[\frac{1}{\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2}]=0 \end {align} \tag{16}$$
となって、第1項は\(r\)のみの関数で第2項は\(\theta\)と\(\phi\)のみの関数だと分かります。このように、第1項と第2項の変数が異なる場合、方程式(16)が解をもつには各項が定数である必要があります。したがって、\(\beta\)を定数とおけば(16)式は、
$$-\frac{1}{R(r)}[\frac{d}{d r}(r^2\frac{dR}{dr})+\frac{2m_{\,e}r^2}{\hbar^2}(\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r}+E)R(r)]=-\beta \tag{17}$$
$$-\frac{1}{Y(\theta ,\phi )}[\frac{1}{\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2}]=\beta \tag{18}$$
のように分離できます。このとき、各項の頭にあった\(\hbar^2\)は定数なので\(\beta\)の中に入れました。したがって、(17)式は水素電子の半径に関する式として、(18)式は水素電子の角度に関する式としてそれぞれ与えられたことになります。このとき、(17)式を動径方程式と呼びます。
ところで、剛体回転子の波動関数\(Y(\theta ,\phi )\)についてのシュレディンガー方程式は、
$$-\frac{\hbar^2}{2I}[\frac{1}{\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta\frac{\partial Y}{\partial \theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}(\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2})]=EY(\theta ,\phi) \tag{19}$$
で与えられます。剛体回転子とは、2つの質点があいだの距離を一定に保ちながら回転しているモデルのことを指します。このとき、\(I\)は剛体回転子の慣性モーメントです。詳しいことは以下の記事を参考にしてください。
参考:剛体回転子のエネルギー準位と慣性モーメント
(19)式の両辺に\(2I/[\hbar^2Y(\theta ,\phi)]\)をかけてみると、
$$-\frac{1}{Y(\theta ,\phi)}[\frac{1}{\sin \theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta\frac{\partial Y}{\partial \theta})+\frac{1}{\sin^2\theta}(\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2})]=\frac{2IE}{\hbar^2} \tag{20}$$
となって、
$$\beta=\frac{2IE}{\hbar^2} \tag{21}$$
とおけば、まさに(18)式と一致します。したがって、水素電子の波動関数の角度部分\(Y(\theta ,\phi)\)は剛体回転子のシュレディンガー方程式の解と一致することが分かりました。
今回の解説はここまでにし、次回の記事では(18)式を具体的に解いていきます。具体的には、(17)式がさらに角度\(\theta\)依存式と角度\(\phi\)依存式の積で表されることを確認し、角度\(\phi\)依存式の解を計算します。